この記事では、

病院で栄養士として働いてみたいな!どんな仕事内容なんだろう?
と思っている人へ向けて、僕が働いた経験をもとに、委託給食会社の病院での仕事内容を書いています!
はじめに:委託給食会社と栄養士
委託給食会社と言うのは、契約先の建物の厨房を借りて食事を作るお仕事をする会社です。そのため、契約先の数だけ働く場があります。
契約先で多いのは病院・老人ホーム・社員食堂・小中学校・幼稚園・保育園・学生寮などで、場所によって働く時間や内容が全く違います。早朝から出勤が必要だったり、土日祝休みがあったり、献立作成の仕事があったりなかったり。一緒に働く人の性別や年齢も変わってきます。
記事の内容を参考に、委託給食会社における病院の栄養士という仕事について、自分が思う仕事内容なのか、自分がどんな人とどういう仕事がしたいのか、理想のライフスタイルに合うのかなどを考える際に参考にしてみてください!
病院栄養士の勤務条件
勤務時間目安:5時~22時(この時間内で8~10時間勤務)
勤務体系:シフト制
休みの目安:月6~9回。年末年始やお盆の休みはない。急な欠勤で出勤をお願いされることも。
職場の性別・年齢層:栄養士やパートさんは40代~60代女性が多め。病院の規模にもよるが、男性はいて1~2人で40代以降の調理師が多い。若年層は3年くらいで転勤となることが多く、若い年代は少ない。

病院の食事・調理概要
食事について
病院の食事は、特別な栄養制限のない「一般食」と、病気の人のための「治療食」があります。治療食は、病気に応じてエネルギー・塩分・たんぱく質・脂質などを制限した食事になっています。
それぞれの食事について、「約束食事箋」といって病院側から1ヶ月間に提供しなければならない栄養価の提示があります。その数値の範囲に収まるように献立を作成するため、病気に対する栄養の知識は必要になります。
調理について
栄養士が調理することはあまりありません。
人数不足の場合は調理しますが、基本は担当の調理師さんがしっかり作ってくれる場合が多いです。
調理している時間帯、栄養士は入退院した患者さんの食札管理や献立作成、食材の納品などを行ないます。
その後、出来上がった料理の味見や仕上がり状態のチェックをします。

食事の詳細
一般食
【常食】
消化機能に問題のない、普通の食事が食べられる人のための食事。
【軟菜食】
胃が弱かったり、噛む力が低下した人向けの食事。
ご飯は柔らかくし、お粥にすることもある。おかずは柔らかく煮る・蒸すなどして油を抑えたものにする。ごぼうやれんこんなど、固い食材や繊維の多い食材は避ける。
【きざみ食】
噛む力が低下した人向けの食事。
料理や食材を1cmほどに刻んで提供する。これもごぼうやれんこんなど、食べにくい食材は避ける。
【ミキサー食】
噛む力がなかったり、飲み込む力がかなり低下した人向けの食事。食べるものを全てミキサーにかける。お粥やおかずは全てペースト状とし、とろみ剤などを使って食べやすくする。
【流動食】
喫食や消化機能に関わる手術後や、胃が弱い人向けの食事。
重湯(お粥の上澄み)や具なしの汁、ヨーグルト等を提供する。
【嚥下訓練食】
飲み込む力や噛む力が弱った人の食事機能向上を目的とした食事。
咀嚼や嚥下力のレベルによって食べやすさを調整して訓練を行なう。
治療食
【エネルギーコントロール食】
糖尿病や肥満、脂質異常症の患者さんに向けた食事。
炭水化物・脂質・たんぱく質のバランスがとれた食事で、エネルギーは控えめに設定されている。病態によって塩分を減らす場合もある。
糖尿病食は別枠で設定することもあり、DM食などと呼ばれる。
【たんぱく・塩分コントロール食】
腎臓や肝臓に疾患のある患者さんに向けた食事。
病状によってたんぱく質や塩分量が設定されていて、段階別に調理して提供する。
【脂質コントロール食】
膵臓や胆嚢に疾患のある患者さんに向けた食事。
揚げ物や油の多い料理は制限されるが、それでも美味しい料理を出せるよう、食材や調理方法を工夫する。
【貧血食】
鉄欠乏性貧血や、その他原因における貧血の患者さんに向けた食事。
鉄分・ビタミンCを多く含む食材を使い、バランスのとれた献立を提供する。偏食や無理なダイエットが原因の場合も多く、退院後の食生活の改善も必要。
【低残渣食】
胃腸に疾患のある患者さんに向けた食事。
症状によって程度は変わるが、消化に負担のかかる食物繊維や脂質を減らし、刺激物や冷たいものも控えるような献立にする。
【術後食】
胃や腸の手術後の患者さんに向けた食事。
消化吸収能力が落ちているので、具材を煮込んだり刻んだりして消化の良い食事を提供する。また、1回の食事量を減らし、食事回数を増やして負担を減らす食べ方をする。
—————————————–

こんなにいっぱいあるんだねぇ。病院の栄養士さんってすごーい!

ここで紹介したのが全部じゃないぞ。
各コントロール食は、病態によって更に細かく食事が分けられるんだ。

ちなみに病院のご飯は昔と比べてめちゃくちゃ美味しくなってるんだってな。
調理するほうもすごいな!
この他にも、病院によって様々な食種を設定し対応しています。
また、個別にアレルギーや好き嫌い対応をする「禁止食」などもあり、対応は多岐にわたります。
病院での栄養士の業務内容
病院での委託栄養士の業務は、「献立作成」「発注」「調理」「盛付け」「配膳前チェック」などを行ないます。
数多くある病気を理解して献立を作り、作った料理を間違えることなく患者さんのもとに届け、食べてもらうのが仕事になりますから、病院の栄養士・調理師は重要な存在です。

献立作成
・病院側でやる場合もあれば、委託側でやる場合もある。
・前述のように、たくさんいる入院患者さんの病態に合わせた献立を考える。多いと20~30食種あることもあり、結構大変。
・委託の栄養士の場合、献立作成だけではなく盛付けや調理をする場合がほとんど。そのため食事提供の合間を縫って時間をつくり、糖質を抑える糖尿病食、タンパク質や水分を抑える腎臓病食、脂質を抑える膵臓病食など病態に合わせた献立作成を行なうことになる。結構ハード。
・でも病院を経験しておけばどこ行っても大丈夫というくらい、献立を作る力や現場をみる力はつく。
発注
・病院側でやる場合もあれば、委託側でやる場合もある。
・病院側発注の場合、調理をするのは委託側なので在庫分がわからず発注してしまい、在庫があふれることもある。そうならないよう、委託側から積極的に病院側とコミュニケーションをとる気持ちが大切。
・委託側発注の場合は、在庫を気にしながら発注できればOK。突発的な入院で食材が足りなくならないよう、計算して発注しておくのを忘れずに。
調理
・委託側のメイン業務。アレルギー食などは責任が重いため、病院側で調理することもある。
・配膳前に病院側の栄養士さんが味のチェックに来る場合が多い。病院食は塩分や水分にキビシイので、レシピ通りにつくれていない(味が濃くなってしまった)場合は作り直し、ということもある。最終的に味を決めるのは病院側なので、早めに味見のお願いをしておいたほうがよい。
・食数の多い病院だと、常食(通常の食事)と治療食(病気の人のための食事)の調理担当者を分けて調理をする。
・栄養士は、調理の進行状況を見ながら遅れている場所に指示を出したり、自分が代わりに調理したりするなど現場を回していく役割に当たることが多い。
盛付け・配膳
・出来上がった料理を病態別に食器に盛付ける。見た目は同じでも、片方は脂質を抑えるためにノンオイルドレッシングを使っているなど、使う調味料が違う場合があるので慎重に作業する。
・盛り付けたら、患者さんの病気と食事内容が書かれた食札を見ながら食器をトレーに乗せる。ここで間違えるとその患者さんが食べてはいけない食事が行ってしまう可能性があるので、一番の注意が必要。
栄養指導
・委託側で栄養指導がしたくて管理栄養士を取得する人も多いが、ほとんどの場合病院側の業務。委託の栄養士が出向して行なうケースもあるが、ごく稀。
・お願いすれば、栄養指導しているところを見学させてもらえることもある。
・病院側の管理栄養士が院内で栄養セミナーを開くこともあるので、それを聞かせてもらうだけでもよい経験になる。

やること多すぎて痩せちゃうよ~

シバは少し痩せたほうがいいんじゃないか?
病院の栄養士、やりがいはありそうだな!
おわりに
病院の栄養士は献立の種類がたくさんあり、覚えることが多く大変だと僕は思っています。
献立以外にも、調理や盛付けで人が足りていないことは日常茶飯事で、調理や盛付け、洗浄に入ることも普通の話。その中で献立や発注、採算管理なんかもやるのでほんとに時間が足りないよ!と毎日思うくらいの忙しさです。
でもやっぱり経験しておくとかなりスキルアップになるので、献立・発注・調理・盛付けなど現場力をつけたい人にはおすすめです。
委託で働いていると管理栄養士としての業務はなかなかできませんが、身近に病院側の管理栄養士さんがいるので、良い関係が築ければ栄養指導やセミナーなどの管理栄養士業務を見せてもらえることもあります。
将来的に病院側の管理栄養士になりたい場合は、病院側の管理栄養士さんと仲良くなっておくと良いことがあるかもしれません!
ということで、病院での委託栄養士の仕事内容についての記事でした!
ここに書いたことが全てではありませんが、結構細かく書いたので、仕事の選択肢として参考にしてもらえたら嬉しいです!
他の業態についても書いていきますので、よかったら読んでみてくださいね〜。
*他の業態の記事はこちら
老人ホーム

社員食堂

小・中学校

幼稚園・保育園
学生寮
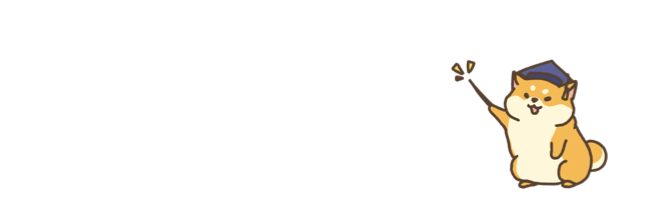





















コメント